INSIDER【INSIDE VIEW】「暮らしに潜む“クラスター”のリスク」
- NTB 南西テレビ【架空放送局】
- 2020年4月25日
- 読了時間: 4分
2020/04/24放送
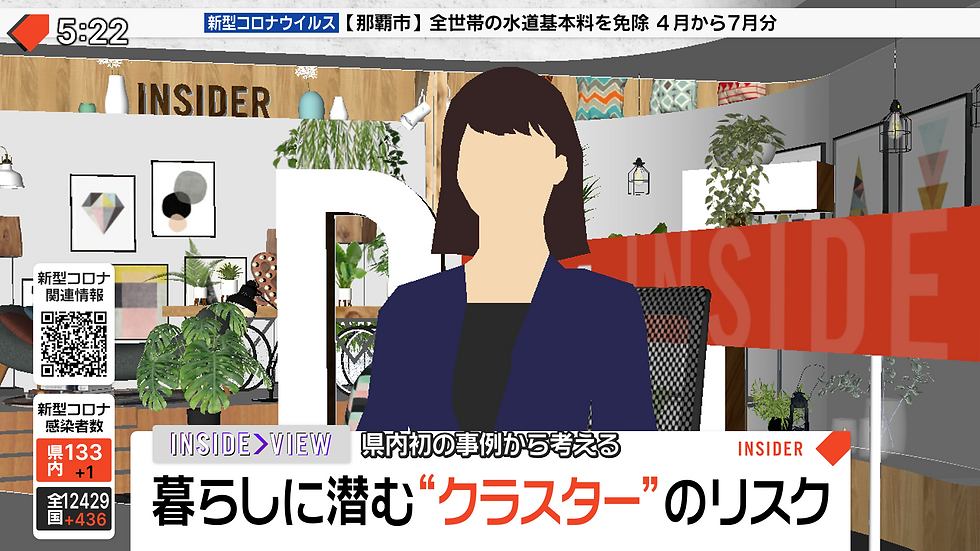
今月21日に判明した県内初の“クラスター”。
新型コロナウイルスの感染が拡大するなかで、この“クラスター(集団感染)”防止が全国的に呼び掛けられています。
感染してしまう、させてしまう前に、決して他人事では済まない私たちの暮らしにも潜むそのリスクについて取材しました。
今月21日に判明した県内初の
高齢者らによる“クラスター”。いわゆる集団感染。
国内外の大都市圏では以前から呼び掛けられていた
この“クラスター”の危険性だが、ついに県内でもその事例が報告されたのだ。
21日に県が発表した高齢者らの“クラスター”。
また、新型コロナウイルス感染により今月15日に報告された県内1人目の死者も、
この“クラスター”が起きた会合の参加者だったことがわかっている。
そのきっかけとなった沖縄市の地主会の会議が開催されていたのは、今月7日。
それから発表までの2週間。
どのようにして感染は広がり、“クラスター”は起きてしまったのか。

会議には60代から70代の約30人が参加し、1時間半程度開催されたという。
40人程度が収容できるスペースに机を並べ、1つの机あたり2~3人で座っていた。
「コロナ対策」として感覚をあけて座るようにしていたというが、
その日は冷え込んでいたことから十分に換気を行っていなかったことが取材の中で明らかになった。

時系列でみていくと、会議が開催されたのは今月7日。
9日には会議に参加していた70代の男性が入院。
15日にはこの男性が死亡。同時に新たに2人の陽性が判明した。
地主会は県に対し対応を問い合わせたが、県は
「1人目の発症日は会議出席から2日後で濃厚接触に該当しない」と説明した。
これは濃厚接触が「発症した日から」という当時の定義によるもので、
この時点で消毒や会議参加者の自宅待機など、踏み込んだ指導はなかったという。
国立感染症研究所は後に20日付で
「症状が出る2日前からの接触」と濃厚接触の定義を変更している。

15日時点で参加者の感染が相次いで判明したことから、地主会の不安は高まっていた。
保健所から明確な指導がないまま、16日には独自の判断で事務所を閉鎖。
取材の中では、自主判断で自宅待機している人もいたが、その後も他の会合に参加した人もいたことがわかった。
17日になると、県は地主会幹部に対し「発症前でも濃厚接触にあたる」と連絡し
7日の会議の参加者名簿の提出を求め、地主会は20日に名簿を提出した。
翌日21日に県が“クラスター発生”を発表するまでにも
18日に新たに会議参加者の中から2人の陽性が判明。
22日の時点でこの“クラスター”による感染者は7人となった。

今回話を伺った、会議に参加した男性は―
「(会議で)新型コロナの話は出たが、せきなどの症状が出ている人はおらず、まさかという気持ち。振り返ると甘かった、油断していた点もある」
と話した。

今回の事例をまとめると、
会議参加者1人との濃厚接触者として参加者以外の2人の感染も明らかになっている。
また、今回の事例で現在でも1人の患者が重症で治療中だという。

“クラスター”とは、
同一の場において5人以上の感染が明らかとなった状況を指すとされています。
一度“クラスター”が起きてしまうことで、それぞれが二次的な感染を引き起こし
さらなる大規模な集団感染につながりかねず、
いかに早くクラスターを見つけ、対策を講じることが感染拡大の分かれ目とされています。
県外ではライブハウスや医療機関、スポーツジム、飲食店などで発生が確認されています。
集団感染が起こりやすい条件として、
換気の悪さ、人が密集して過ごす空間、不特定多数の人が触れる可能性がある場所として、
このような「3つの“密”」、
「密閉」「密集」「密接」の「3密」を避けるよう呼び掛けています。
今回発生した“クラスター”のような集会の場面以外にも、
私たちの暮らしにどのような危険が潜んでいるのか考えなければなりません。
日用品や食品などの生活必需品を買いにスーパーに行くとき、
モノレールやバスを利用するとき、親戚一同で集まるとき…
これまでの“普通の生活”のままではそのリスクを回避することができません。
一人ひとりが「3密」を避ける行動をするだけでなく、
マスクの着用や手指の消毒といった正しいことをしっかり行うことで
確実に感染を防ぐことができます。
また、重症化リスクの高い高齢者の中には、
ビデオ会議などの方法を知らない人も大勢いるはずです。
地域や家族の若い世代が周囲の高齢者をサポートし、
ウイルスから守ることがいっそう重要になってきているのではないでしょうか。







コメント